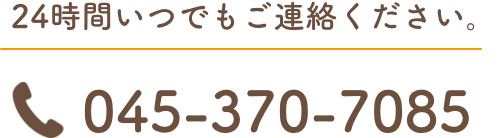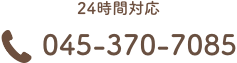お知らせ&ブログ
デジタル遺産の整理と、もしもに備える生前整理
パソコンやスマートホン、インターネットの利用が当たり前の世の中になりました。それに伴い、「デジタル遺産」が増え、パスワードが分からずアクセスできない、そもそもどこにデータが存在しているのか分からない、といったご遺族のトラブルも増加しています。
この記事では、こういったトラブルを避けるために、デジタル遺産の生前整理についてご紹介します。まずはご自身にどれだけのデジタル遺産があるのかを把握し、起こりそうなトラブルを考えてみましょう。そして、そのトラブルを回避するために、どのような生前整理の方法があるのかを確認してください。
そもそもデジタル遺産とは?
デジタル遺産とは、故人様が保有していた「データ形式の財産」のことです。デジタル遺品とも言われ、具体的には、次のようなものが挙げられます。
・スマートホンやパソコン内にあるデータ
・クラウドサービスに保存されたデータ
・SNSのアカウント
・ネット銀行やネット証券
・メールのアカウント
・アマゾン、楽天市場、動画配信サービスなどのアカウント
・ネット上のサービスで貯まったポイント など
データでの保存やインターネットの利用が当たり前になった現在では、本人でも全てを把握するのは難しいかもしれません。生前はとても便利ですが、終活を意識しているなら少しずつ整理を進めてみると良いでしょう。
デジタル遺産に関連して起こるトラブル
デジタル遺産の特性は「アクセスしないと存在していることすら分からない」ということでしょう。そのために、データを管理していた本人にしかわからないトラブルが起こってしまうのです。
・スマートホンやパソコンのロック解除ができない
・どのネット銀行やネット証券を利用していたのか分からない
・サービスの解約が出来ず、更新料金が引き落とされ続けてしまう
・SNSのなりすまし被害にあう など
交流があった人の連絡先がスマートホンなどに集約されている場合、ロックを解除できず、亡くなったことを知らせる連絡がとれない、という事態が起こってしまいます。
また、ネット銀行やネット証券にある財産も相続の対象になりますが、問い合わせ先が分からない、存在すら知らなかったといったトラブルも増加しています。
こういったトラブルを防ぐためには、しっかりと生前整理を行っておくことが大切です。
トラブルを防ぐため、デジタル遺産の生前整理を
デジタル遺産にまつわるトラブルを防ぐためには、どうすればいいのでしょうか。生前整理の方法について考えてみましょう。
●デジタル形式で残すものは、最小限にとどめる
デジタル遺産は、増えれば増えるほど管理が大変です。あなたの死後、家族にかかる負担のことを考えると、デジタル遺産となるものは早めに整理をし、本当に必要なものだけを残しておくのがいいでしょう。
具体的には、以下のような対策が挙げられます。
・パソコンやスマートホンの、いらないデータは削除する
・ネット上の利用していないサービスは解約する
・見ることのないSNSのアカウントは削除する
・ネット銀行、ネット証券は一つに絞る など
●家族にパソコンやスマートホンのデータについて伝えておく
知人の連絡先や思い出の写真をパソコン・スマートホンに保存している場合、そのことを家族に伝えておくことが大切です。知人の連絡先が分かればあなたが亡くなったことを速やかに伝えられますし、最近の写真から遺影を作ることも可能です。
逆に考えれば、知人の連絡先が分からない、最近の写真もないとなると、葬儀の準備をする家族は大変な思いをすることになるでしょう。
●エンディングノートを書く
パソコン・スマートホンのパスワードやSNSのアカウントなど、生前のうちは家族に知られたくないデジタル遺産もあることでしょう。そのような場合は、エンディングノートを作成しておくことが有効です。エンディングノートを通じてデジタル遺産の存在を知らせることで、生前のプライバシーは守られます。
ただし、パスワードを変えたりアカウントを削除したりと、デジタル遺産の内容に変化があった場合には、エンディングノートの情報も更新しておかなければなりません。エンディングノートに書かれていることが常に最新の情報になるよう注意しましょう。
●自動削除の機能があるソフトを導入する
自分の死後であっても家族に見られたくない、知られたくないデータがある場合には、ファイルを自動削除する機能があるソフトを導入しておくのも一つの手です。自動削除のソフトとは、一定の期間パソコンが開かれなかったときに自動でファイルを削除してくれるというものです。
●死後事務委任契約を結ぶ
デジタル遺産のことを全く家族に知られたくないという場合には、専門の知識を持った信頼できる相手と死後事務委任契約を結ぶといいでしょう。死後事務委任契約とは、多岐にわたる死後の事務処理を任せられるもので、契約の内容は幅広く、自由に決めることができます。
例えば、デジタル遺産に関しては、以下のような要望を出せます。
・自分の死後、パソコンの中身を見ずに処分してほしい
・SNSのアカウントを追悼アカウントに移行してほしい
・ネット上のサービスを解約し未払金を精算してほしい
こういった指示は遺言書では効力がないものですから、より確実にデジタル遺産の処理をしたい場合には死後事務委任契約が有効です。
死後事務委任契約を結ぶ相手は、親族や友人など誰でも可能です。しかし、死後事務には煩雑なものも多いため、周りの方に負担をかけるのが気になってしまうなら、費用はかかりますが、弁護士や行政書士などの専門家に依頼するといいでしょう。
死後事務委任契約に関する詳しいお話はこちらのブログでもしています。ご興味がおありの方はぜひご覧ください!↓
デジタル遺産の生前整理は定期的に行いましょう
デジタル遺産は、一度に整理をしようとすると膨大な時間がかかってしまいます。また、一度整理をしても生活を続けていく以上、少しずつ増えてしまうものでもあります。そのため、可能ならば半年に1回、年に1回などタイミングを決めて定期的に整理をしておくことをおすすめします。
残されたご家族が苦労されないように、そしてご自身のプライバシーが尊重されるように、ぜひデジタル遺産の生前整理を進めてみてください。
テラスライフでは、専門の知識を持ったスタッフによる死後事務委任契約の締結を行っております。死後事務委任契約を結ぶことで、契約内容に則り、適切な対応でお客様のデジタル遺産の処理をさせていただきますので、ご興味がおありの方はぜひお気軽にご相談ください。
また、死後事務委任契約ではデジタル遺産の処理の他にも、賃貸借物件の家賃支払い・契約解除、通常の遺品整理、葬儀や供養に関することなどもお客様のご希望にそって対応可能です。どのようなご希望があるか、そのためにはどんな契約が必要か、専門の知識を持ったスタッフがしっかりとお話しを伺ったうえでプランをご提案致しますので、安心してご相談ください。もちろん、ご相談はいつでも無料です。
テラスライフ 電話番号:045-370-7085
(監修:行政書士・尾形達也)

- おひとりさま
- おひとり様
- エンディングノート
- コミュニティ
- 不動産分割
- 人生設計
- 介護施設見学の同行
- 仕事付き高齢者向け住宅
- 仕事付き高齢者向け施設
- 任意後見
- 任意後見制度
- 保証人
- 入院
- 入院準備
- 公正証書遺言
- 共済年金
- 喪主代行
- 埋葬手配
- 家族信託
- 年金手続きサポート
- 延命措置
- 想いを伝える
- 成年後見人
- 成年後見制度
- 手術の立ち会い
- 施設見学
- 日常生活を支援
- 死亡一時金の申請
- 死亡届
- 死後事務委任契約
- 法定後見
- 法定後見制度
- 法要代行
- 海洋散骨
- 生前贈与
- 相続
- 相続放棄
- 相続登記
- 相続税
- 相続調査
- 福祉型信託
- 空き家
- 納骨代行
- 終活
- 老後の備え
- 老後資金
- 老齢厚生年金
- 自分の意志
- 自筆証書遺言
- 自筆証書遺言保管制度
- 葬儀サポート
- 要介護
- 要介護認定
- 要支援
- 認知症
- 象族税対策
- 財産管理
- 財産管理のトラブル
- 財産管理委任契約
- 身元保証
- 身元保証人
- 身元引受人
- 身辺監護
- 連帯保証人
- 遺品整理
- 遺族厚生年金
- 遺族基礎年金
- 遺族年金
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議書
- 遺留分
- 遺留分侵害額請求
- 遺言
- 遺言公正証書
- 遺言執行人
- 遺言書
- 遺贈寄付
- 配偶者居住権
- 配偶者短期居住権
- 障害厚生年金
- 高齢者施設