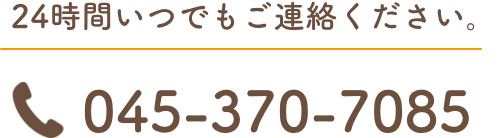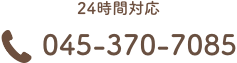お知らせ&ブログ
相続の基本|相続でトラブルにならないために
相続でトラブルが起こるのは一定以上の資産がある一部の人々だけの話だと思ってはいないでしょうか。
実際は、ごく平均的な資産のいわゆる一般家庭のほうが、トラブルの起こるケースは多いのです。
平成30年度のデータによると、遺産分割について裁判で争われた案件のうち、遺産額が1000万円以下の案件が33%、1000万~5000万円が43%となっています。これらを合わせると、遺産分割で争いとなったケースのうち、5000万円以下が76%となります。ちょっと意外な数字だと思いませんか。
この理由は、資産が多くある場合は、不動産・証券・預金などに分散して保有していることが多く分割がしやすいことや、相続人同士で分けたとしても十分な金額になるので不満が生じることが少ないからです。
それに対して相続財産が少ない場合は、実家の不動産が主な資産であるケースが多く、分け方が難しくなります。そのため実家を継いだ子ども以外の家族は取り分が非常に少なくなり、不満が出ることになるのです。
自分の遺した財産が原因で、自分の死後、家族が争うのは本当に残念なことですよね。そうならないためにも相続の基本的な知識を持ち、遺言書などを作成しておくことがとても重要になってくるのです。
相続の基本
相続の方法には、主に次の3つがあります。
・法定相続:民法で定められた人が既定の割合でもらう相続
・遺言による相続:遺言書に従って相続の内容を決める相続
・分割協議による相続:相続人全員で話し合って遺産の分割方法を決める相続
遺言書がある場合は、原則、遺言書に沿って相続は行われます。
対して遺言書がない場合は、相続人同士で話し合って分割協議をするか、民法の定めた法定相続の規定に従って相続を行うことになります。
つまり遺産を受け取れる人は、法定相続人又は受遺者いずれかです。
・法定相続人:
民法で決められた相続人で、故人の配偶者と、子か親か兄弟姉妹等
・受遺者:
遺言書で遺産を譲り受けるように指定された人
遺言書は故人様の生前の意思を尊重するべく優先されますが、法定相続人(兄弟、姉妹を除く)には、遺留分として遺産の一定割合を受け取る権利があります。
そのため、遺言書で財産の全てを誰かに譲ると記してあったとしても、法定相続人はその中から遺留分の受取を主張することが可能です。
おひとりさまの相続
これまでずっと独身だった方や配偶者に先立たれて子どもがいない方といった、いわゆる「おひとりさま」といわれる方の相続はどうなるのでしょうか。
子どもや配偶者のいないおひとりさまが亡くなった場合、遺産を相続する法定相続人は、親、兄弟、甥、姪といった人々になります。子どもがいないから相続は関係ない、ということではないので注意しましょう。
もし、こうした家族や親戚などの法定相続人が一人もいない場合には、民法の規定により国庫に納付という形になります。こうした国庫納付の額は毎年増えており、2017年には525億円にもなっています。
また、家族や親戚がいない場合でも、特別縁故者の申し立てが認められると、遺産を受け取ることが可能になります。
特別縁故者とは下記のような人です。
1.故人様と生計をともにしていた人物
2.故人様の看護や介護にあったった人物
3.故人様と親兄弟のように親密な関係であった人物
4.故人様と縁の深い法人
特別縁故者として認められるには、裁判所に申し立てをします。その際に認められるか否かは裁判所の判断次第であるのに加え、申し立てには相応の費用も時間も要するので注意が必要です。
おひとりさまの生活であっても、お世話をしてくれた人に感謝の想いとともに財産を渡したいということであれば、遺言書作成などでしっかりと遺産相続の準備をしておいたほうが確実と言えるでしょう。
遺言書の作成について、なぜ作成したほうがいいのか、どのような内容を書けばいいのかという点につきましては、こちらの記事で詳しくお話ししておりますので、ぜひ一度ご覧ください。↓
なぜ遺言書を作成したほうがいいのか|遺言書に書いて法的効力を発揮すること・しないこと
相続は100人いれば100通りのお悩みやご心配事が存在します。ぜひ一度テラスライフにご相談ください。資格を有した専門家が親身になってしっかりとサポートをさせていただきます。
ご相談のお電話はこちらへ ↓
テラスライフ 045-370-7085
(監修・行政書士・尾形達也 )
- おひとりさま
- 相続

- おひとりさま
- おひとり様
- エンディングノート
- コミュニティ
- 不動産分割
- 人生設計
- 介護施設見学の同行
- 仕事付き高齢者向け住宅
- 仕事付き高齢者向け施設
- 任意後見
- 任意後見制度
- 保証人
- 入院
- 入院準備
- 公正証書遺言
- 共済年金
- 喪主代行
- 埋葬手配
- 家族信託
- 年金手続きサポート
- 延命措置
- 想いを伝える
- 成年後見人
- 成年後見制度
- 手術の立ち会い
- 施設見学
- 日常生活を支援
- 死亡一時金の申請
- 死亡届
- 死後事務委任契約
- 法定後見
- 法定後見制度
- 法要代行
- 海洋散骨
- 生前贈与
- 相続
- 相続放棄
- 相続登記
- 相続税
- 相続調査
- 福祉型信託
- 空き家
- 納骨代行
- 終活
- 老後の備え
- 老後資金
- 老齢厚生年金
- 自分の意志
- 自筆証書遺言
- 自筆証書遺言保管制度
- 葬儀サポート
- 要介護
- 要介護認定
- 要支援
- 認知症
- 象族税対策
- 財産管理
- 財産管理のトラブル
- 財産管理委任契約
- 身元保証
- 身元保証人
- 身元引受人
- 身辺監護
- 連帯保証人
- 遺品整理
- 遺族厚生年金
- 遺族基礎年金
- 遺族年金
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議書
- 遺留分
- 遺留分侵害額請求
- 遺言
- 遺言公正証書
- 遺言執行人
- 遺言書
- 遺贈寄付
- 配偶者居住権
- 配偶者短期居住権
- 障害厚生年金
- 高齢者施設