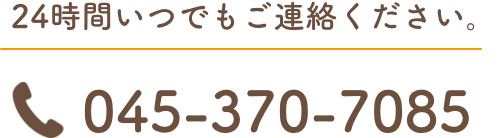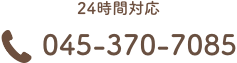お知らせ&ブログ
万一の時にご遺族の生活を助ける、それが遺族年金です
一家の大黒柱であったご家族が亡くなってしまったとき、残されたご家族は、悲しみの感情と共に、将来への不安を覚えることになるでしょう。特に、小さなお子様がいる場合などは、今後の生活資金のことなどが、心配になるのは間違いありません。
そうした万が一に備えるのが生命保険ではありますが、全ての人が加入しているものでもありません。また加入していたとしても、十分な補償が得られない場合もあります。
そんな時に頼りになるのが、私たちが加入している公的年金です。公的年金には、ご遺族の生活を助けるための役割があります。それが遺族年金です。
この記事では遺族年金について、どのような制度なのか、申請するにはどうすればいいのか、といったことを具体的にお話ししていきます。

遺族年金とは
遺族年金は、国民年金または厚生年金に加入していた方が亡くなった際に、その方の配偶者や子どもなど、生計を維持されていたご遺族に支給される年金です。
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、亡くなった方の年金の納付状況などによって、どちらか一方または両方の年金が支給されます。
遺族年金はその他の日本の公的年金と同様に2階建ての仕組みになっており、1階部分が「遺族基礎年金」、2階部分が「遺族厚生年金」となっています。遺族基礎年金は国民年金の一部で、遺族厚生年金は会社員や公務員が加入している厚生年金部分となります。
その他、両者の特徴は以下の通りです。
遺族基礎年金
18歳未満の子ども(障害がある場合は20歳未満)がいる場合に、配偶者または子どもに支給されます。
遺族厚生年金
子どもがいるかいないかに関わらず、厚生年金に加入していた場合に支給されます。
遺族基礎年金
【遺族基礎年金が支給される要件】
遺族基礎年金を受給するためには、亡くなった方が死亡日において次のいずれかの要件に該当し、かつ支給対象となるご遺族がいることが必要です。
①国民年金の被保険者であること。
②国民年金の被保険者であった人で、死亡当時日本国内に住民登録があり60歳以上65歳未満であること。
③老齢基礎年金の受給資格を満たしていること。
④老齢基礎年金の受給者であること。
【遺族基礎年金の対象者】
遺族基礎年金を受け取れるのは、子どもがいる配偶者と、子どもです。
また、子どもの要件は下記のとおりです。
①18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
②20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
亡くなった方に生計を維持されていた、ということが条件ですので、子どもは未婚である必要があります。
【遺族基礎年金の受給額(令和4年現在)】
令和4年4月の段階では、遺族基礎年金の受給額は、下記の式で計算されています。
①子がいる配偶者が受け取るとき
77万7,800円+子の加算額
②子が受け取るとき(次の金額を子の数で割った額が一人あたりの額)
77万7,800円+2人目以降の子の加算額
子の人数加算の金額は、子が2人までは1人あたり22万3,800円、3人目以降は一人あたり7万4,600円が加算されます。
例)配偶者+子が3人の場合
77万7,800円+(22万3,800円×2)+7万4,600円=130万円
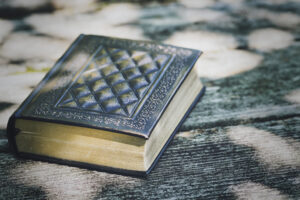
遺族厚生年金
【遺族厚生年金が支給される要件】
遺族厚生年金は、厚生年金を納めていた会社員や公務員などが亡くなった際に、そのご遺族に支給される年金です。
具体的には、亡くなった人が以下の5項目のうち、いずれかを満たしている必要があります。
①厚生年金の被保険者である間に亡くなった。
②厚生年金の被保険者期間中に初診日のある傷病が原因で、その初診日から5年以内に死亡した。
③1級または2級の障害厚生年金を受給している。
④老齢厚生年金を受給している。
⑤老齢厚生年金の受給資格を満たしている。
【遺族厚生年金の対象者】
遺族厚生年金の対象となるのは、亡くなった方の収入で生計をたてていた配偶者、子、父母、祖父母、孫です。その中でも、配偶者と子どもが優先され、次に父母、孫、そして祖父母という順番になります。
そして、配偶者または子どもは、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給することが可能です。ただし、受給する配偶者が子どものいない30歳未満の妻であれば5年間しか受給できず、55歳未満の夫にはそもそも受給権がありません。
【遺族厚生年金の受給額】
遺族厚生年金の受給額は、老齢厚生年金の3/4の金額となります。ただし、詳細な受給額の算出にはとても複雑な計算が必要となりますので、金額を把握するには、専門家に相談するか年金事務所で確認するといいでしょう。
遺族年金の申請
遺族基礎年金の申請先は、住所地の市区町村役場の窓口あるいは、お近くの年金事務所や年金相談センターになります。
遺族厚生年金の場合は、年金事務所あるいは年金相談センターです。
申請書がそれぞれの窓口にある他、インターネットからダウンロードして記入することも可能です。
また、申請時に必要な書類は以下の通りです。
・戸籍謄本
・年金手帳
・世帯全員の住民票の写し(またはマイナンバー)
・死亡者の住民票の除票
・請求者の収入が確認できる書類
・生計維持認定のため所得証明書
・子の収入が確認できる書類(義務教育中は不要)
・死亡診断書
・受取先金融機関の通帳
その他、故人様の死亡原因や状況によっては、追加で必要な書類もございますので、その点もご注意ください。

遺族年金の申請は専門家への依頼がおすすめ
遺族年金手続きは、社会保険労務士や行政書士等の専門家に代行を依頼することも可能です。ご自身で書類を確認して不備なく申請するのは大変だという場合は、専門家に依頼することも検討してみてはいかがでしょうか。
テラスライフでは、専門のスタッフが遺族年金をはじめ、障害年金や共済年金など各種年金の申請の代行を承っております。年金の申請手続きは、慣れていない方には大変な労力となりますので、少しでもご不安がおありの場合は、ぜひお気軽にご相談ください。
専門のスタッフが親身になってお話を伺い、最適なサポートをご提案致します。もちろん、ご相談はいつでも無料です。お気軽にお問合せください。
テラスライフ電話番号:045-370-7085
(監修:行政書士・尾形達也)
▼その他の年金やその申請サポートに関する記事はこちら!▼
- 年金手続きサポート
- 遺族厚生年金
- 遺族基礎年金
- 遺族年金

- おひとりさま
- おひとり様
- エンディングノート
- コミュニティ
- 不動産分割
- 人生設計
- 介護施設見学の同行
- 仕事付き高齢者向け住宅
- 仕事付き高齢者向け施設
- 任意後見
- 任意後見制度
- 保証人
- 入院
- 入院準備
- 公正証書遺言
- 共済年金
- 喪主代行
- 埋葬手配
- 家族信託
- 年金手続きサポート
- 延命措置
- 想いを伝える
- 成年後見人
- 成年後見制度
- 手術の立ち会い
- 施設見学
- 日常生活を支援
- 死亡一時金の申請
- 死亡届
- 死後事務委任契約
- 法定後見
- 法定後見制度
- 法要代行
- 海洋散骨
- 生前贈与
- 相続
- 相続放棄
- 相続登記
- 相続税
- 相続調査
- 福祉型信託
- 空き家
- 納骨代行
- 終活
- 老後の備え
- 老後資金
- 老齢厚生年金
- 自分の意志
- 自筆証書遺言
- 自筆証書遺言保管制度
- 葬儀サポート
- 要介護
- 要介護認定
- 要支援
- 認知症
- 象族税対策
- 財産管理
- 財産管理のトラブル
- 財産管理委任契約
- 身元保証
- 身元保証人
- 身元引受人
- 身辺監護
- 連帯保証人
- 遺品整理
- 遺族厚生年金
- 遺族基礎年金
- 遺族年金
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議書
- 遺留分
- 遺留分侵害額請求
- 遺言
- 遺言公正証書
- 遺言執行人
- 遺言書
- 遺贈寄付
- 配偶者居住権
- 配偶者短期居住権
- 障害厚生年金
- 高齢者施設