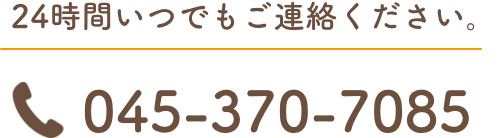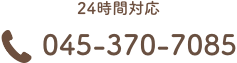お知らせ&ブログ
おひとりさま高齢者の財産管理問題
超高齢化社会の大きな問題のひとつが、「おひとりさま」といわれる単身高齢者の財産管理をどうするかということです。
高齢化が進むことで、認知機能に問題を抱える人の割合もまた増えつつあります。手元のお金や財産の管理が難しくなり、トラブルになるケースも少なくありません。

認知症などにより意思能力がなくなってしまうと、契約などの法律行為を有効に行うことができなくなってしまうため、預貯金の引き出しや資産の運用、売却などができなくなる、つまり資産が凍結されるリスクがあります。
また、判断能力が衰えていくことで、詐欺被害など、犯罪に巻き込まれてしまうことも考えられます。法人を除く詐欺被害者のうち、高齢者(65歳以上)が占める割合は85.7%。判断能力が低下した高齢者が詐欺の標的になっていることは明らかです。
65歳以上の5人に1人が認知症になるとも言われているこの先の社会において、この問題は誰にでも起こり得ることでしょう。
お元気で意思能力があるうちに、自分の財産の管理をどうするのか、この機会に考えてみてはいかがでしょうか?

高齢化する日本社会
日本社会は、長らく少子高齢化の流れが続いています。65歳以上の割合が全人口の28%を超えており、3人に1人が高齢者であると言われています。
それに加え生き方の多様化から、結婚しない選択をする人が増えており、2020年の国勢調査によると、生涯未婚率(50歳時に一度も結婚をしたことがない方の割合)は男性25.7%、女性16.4%となっています。つまり、男性の4人に1人、女性の6人に1人が生涯未婚ということです。
また、高齢になると先に配偶者を亡くして単身になるケースも多く、高齢化が進むことで、配偶者を亡くした後、長く一人暮らしをする方も増えていきます。

その結果、単身高齢者(65 歳以上)は、1990年には 162 万人でしたが、2015年には 593 万人となりました。そして、2020年には671万7000人に増加し65歳以上の約5人に1人が一人暮らしとなっています。その数は今後も増え続け、2040年には総数が896万3000人になると予想されています。
このように具体的な数字を見ていくと、将来的に自分が「おひとりさま」になることは、誰にとっても決してあり得ない話ではないことがおわかりいただけるでしょう。
そして子や孫、姪や甥など、下の世代に出来るだけ迷惑をかけたくないと思っている場合は特に、意思能力がしっかりとあるうちに、財産回りの整理や管理契約を行っておくことが大切になってくるのです。

財産管理委任契約
単身高齢者が、判断能力があるうちにできる財産管理の方法としては「財産管理委任契約」があります。
財産管理委任契約とは、心身の状態が思わしくないときなどに、自身の財産の管理や福祉サービスの利用手続きなどを、信頼できる人に依頼して代わりに行ってもらう契約です。
財産管理委任契約では、金融機関との取引や、定期的な収入の受け取り、公共料金の支払いといった行為を、受任者が委任者を代理して行います。
財産管理委任契約は、判断能力の低下を前提としてはいないため、判断能力に問題がなければ、誰でも利用することができます。委任する相手についても制限はありません。
また、依頼する財産管理と療養看護の内容や期間は、公序良俗の範囲内で自由に決めることができます。
信頼できる人が身近にいるのであれば、検討してみる価値は十分にあるでしょう。

任意後見制度
財産管理委任契約とセットで利用されることが多いのが「任意後見制度」です。本人の判断能力があるうちに後見人になる人と契約し、判断能力がなくなったときに備えておく制度です。後見人は、契約に沿って本人の財産保護・管理を行います。
例えば、判断能力がしっかりしている間は財産管理委任契約を利用し、判断能力の低下がみられるようになってからは任意後見契約に移行するというようなケースが増えています。
また、任意後見制度も財産管理委任契約と同様に、誰とどのような内容を定めて任意後見の契約をするかは本人の自由です。契約する相手の制限もありません。
ただし、任意後見の契約を結ぶには、必ず公正証書に寄らなければならず、家庭裁判所に申し立てをしたあと、任意後見監督人が選任されます。任意後見監督人とは後見人が権利を濫用しないように置かれるものです。
任意後見制度についての詳しい解説記事はこちら▼
『任意後見制度と法定後見制度|おひとりさまにも大きなメリット!』

死後事務委任と遺言書作成
おひとりさまの心配事には、自分の死後に周りに迷惑をかけず必要な手続きがされるのか、また、遺産相続がきちんと行われるのかということもあるでしょう。上記でご紹介した財産管理委任契約や任意後見制度は、委任する本人が亡くなってしまうと無効になってしまいますので、死後の財産管理には適しません。
では、自分の死後の手続きや財産管理(相続の執行)はどうすれば良いのでしょうか。

死後事務委任契約
自分の死後に必要な事務手続きを、事前に信頼できる人に依頼する制度が「死後事務委任契約」です。
死後事務委任契約を結ぶことで、下記のような事柄を依頼することができます。
◎行政機関での手続き
死亡届、健康保険証の返納、年金の資格喪失届出など
◎葬儀関連の手続き
葬儀社への依頼、葬儀場の手配、火葬許可申請書の提出、菩提寺への納骨・永代供養の手配・海洋散骨の手配など
◎知人・親族への連絡
親族、友人、知人、関係者に対して亡くなったことを連絡
◎利用費用の支払い
家賃・医療費・介護施設費の費用の残金を清算支払い
◎自宅や自室の清掃・片付け
自宅や介護施設の部屋の片付け、家財品や不用品の処分
契約の手続きは、契約内容を公正証書にすることが必要ですが、後見人制度のような家庭裁判所の決定を待つ必要はありません。
ただし、死後事務委任契約は、手続きに関する依頼に限られ、遺産相続に関しては行うことができませんので、ご注意ください。
死後事務委任契約についての詳しい解説記事はこちら▼

遺言書
死後の財産管理となる遺産相続については、生前に自筆で法の規定に則った遺言書を作成しておくか(自筆証書遺言)、公証役場にて公正証書遺言を作成することで、遺言執行人が執り行うようになります。
自身の財産をお世話になった人へ遺したい、あるいはどこかに寄付をしたいなど、おひとりさまにとっても相続は他人事ではありません。意思能力がはっきりとしているうちに、遺言書を作成しておくことで、大切な自分の財産の行方を、自分自身の意思で、しっかりと指定しましょう。
遺言書についての詳しい解説記事はこちら▼
『遺贈寄付とは | 遺言書と死後事務委任契約でできる遺贈寄付』

まとめ
財産管理というとお金持ちだけのことかと思われているかもしれませんが、年齢とともに体を動かすことも大変になりますし、意思能力が低下するのは誰にでも起きることです。
何も対策しないまま漠然とした不安を抱え続けるよりは、この機会にしっかりと向き合って、これからも安心して暮らし続けるための準備を進めてみてはいかがでしょうか。

テラスライフでは、おひとりさまのためのサポートを幅広く承っております。
死後事務や財産管理の委任契約、後見制度の契約、遺言書の作成をはじめ、各種契約の締結サポートから執行まで、お客様のお困り事やご不安を解決できる制度をご紹介しつつ、様々な面でお手伝いさせていただきます。
また、おひとりさまには不可欠な身元保証人代行なども行っておりますので、お気軽にご相談ください。専門の知識を持ったスタッフが、しっかりとお話を伺いながら、対応させていただきます。
もちろん、お見積り・ご相談は無料です。
テラスライフ電話番号:045-370-7085
(監修:行政書士・尾形達也)
- おひとりさま
- 任意後見
- 死後事務委任契約
- 相続
- 終活
- 老後の備え
- 認知症
- 財産管理
- 遺言書

- おひとりさま
- おひとり様
- エンディングノート
- コミュニティ
- 不動産分割
- 人生設計
- 介護施設見学の同行
- 仕事付き高齢者向け住宅
- 仕事付き高齢者向け施設
- 任意後見
- 任意後見制度
- 保証人
- 入院
- 入院準備
- 公正証書遺言
- 共済年金
- 喪主代行
- 埋葬手配
- 家族信託
- 年金手続きサポート
- 延命措置
- 想いを伝える
- 成年後見人
- 成年後見制度
- 手術の立ち会い
- 施設見学
- 日常生活を支援
- 死亡一時金の申請
- 死亡届
- 死後事務委任契約
- 法定後見
- 法定後見制度
- 法要代行
- 海洋散骨
- 生前贈与
- 相続
- 相続放棄
- 相続登記
- 相続税
- 相続調査
- 福祉型信託
- 空き家
- 納骨代行
- 終活
- 老後の備え
- 老後資金
- 老齢厚生年金
- 自分の意志
- 自筆証書遺言
- 自筆証書遺言保管制度
- 葬儀サポート
- 要介護
- 要介護認定
- 要支援
- 認知症
- 象族税対策
- 財産管理
- 財産管理のトラブル
- 財産管理委任契約
- 身元保証
- 身元保証人
- 身元引受人
- 身辺監護
- 連帯保証人
- 遺品整理
- 遺族厚生年金
- 遺族基礎年金
- 遺族年金
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議書
- 遺留分
- 遺留分侵害額請求
- 遺言
- 遺言公正証書
- 遺言執行人
- 遺言書
- 遺贈寄付
- 配偶者居住権
- 配偶者短期居住権
- 障害厚生年金
- 高齢者施設