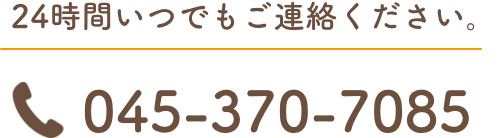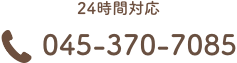お知らせ&ブログ
気になる両親の終活。お互いが元気なうちに確認しておくことは大切です!
ご両親が高齢になると、気になるのが今後のことや万が一の際のことです。年末年始のゆっくりと過ごす時間の中で、終活をどのくらい進めているのか、さりげなく確認してみてはいかがでしょうか。
特に、次の3点についてぜひ話してみてください。
・遺言書の作成
・成年後見制度の利用検討
・生前整理
ご両親の意思をしっかりと受け取る、ご逝去の際にご遺族の負担を減らすという意味で、とても大事な項目になっています。この記事では、それぞれの内容や、なぜ話しておいた方がいいのかなどを解説していきます。

遺言書の作成
高齢のご両親とぜひ話してほしいのが、遺言書についてです。遺言書を用意してもらっておけば、相続の際に多くのトラブルを防ぐことができるので、ご遺族の負担が確実に軽くなるからです。
ここでは、次の2つについてお伝えします。
・なぜ遺言書が必要なのか
・遺言書の作成方法

なぜ遺言書が必要なのか
遺言書を作成しておくと、大きなメリットが2つあります。
・親族同士のトラブルを防げる
・親族の負担を減らせる
相続のトラブルは、裕福な家庭だけに起こる話だという印象はありませんか? しかし、実際は一般的な所得の家庭の方がトラブルは起こりやすいという統計が出ています。つまり、相続トラブルはどのような家族にとっても他人事ではありません。
遺言書があれば、相続について遺された家族が争うこともなくなる上に、遺族が行う手続きの手間も軽減します。遺言書がない場合、まずは遺産がどれだけあるのか、何がどこにあるのかなどを把握するところから相続の手続きを始めなければなりません。さらに、故人様の意思が分からないまま、誰が何を相続するかを決めていかなければならないので、ご遺族には精神的な負担もかかってしまいます。

遺言書の作成方法
遺言書は15歳以上であれば、誰でも作成できます。
遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類がありますので、1つずつその特徴をご紹介します。
・自筆証書遺言
その名の通り、自分で紙に書いて作成した遺言書を「自筆証書遺言」と言います。費用はほとんどかからず、手軽に作成できる遺言書と言えるでしょう。
ただし、きちんと要件を満たしていなければ遺言の効力がなくなってしまう、自分で保管するため紛失や改ざんのリスクがある、というデメリットもありますので、その点はご注意ください。また、そういったデメリットに対応するための「自筆証書遺言保管制度」が2020年に施行されていますので、多少の費用はかかりますが、こちらを検討してみることもおすすめします。
(自筆証書遺言保管制度について詳しいお話はこちら→『知っておきたい自筆証書遺言保管制度』)
・公正証書遺言
公証役場に出向き、公証人立ち合いのもとに作成する遺言を「公正証書遺言」と言います。
数万円の手数料はかかりますが、遺言書が公的なものになるため、遺言が無効となってしまう可能性は殆どありません。また、遺言書が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクも避けられます。
障がいがあるなどの理由で自筆が難しい人でも、公証人に自分の意思を伝えられれば作成できることも、大きな特徴と言えるでしょう。
確実性を考えるなら、大切な遺言は公正証書遺言として作成することをおすすめします。
▼遺言書についてもっと詳しくお知りになりたい方は、ぜひ以下の記事もご確認ください。▼
『なぜ遺言書を作成したほうがいいのか|遺言書に書いて法的効力を発揮すること・しないこと』

成年後見制度の利用検討
成年後見制度とは、判断能力が低下した際、本人に代わって法律に関わる行為を行う「後見人」をつけられる仕組みです。ご両親が認知症になってしまった場合に備え、成年後見制度の利用についても話し合ってみましょう。
ここでは、以下の3つについてお伝えします。
・なぜ成年後見制度が必要なのか
・任意後見制度と法定後見制度の違い
・後見制度は見守り契約と併用を

なぜ成年後見制度が必要なのか
判断能力や認知機能が低下した後でも、契約を結ぶ場面や金銭のやりとりを行わなければならない場面は多々あります。
・介護や福祉サービスの利用契約
・施設への入所や入院時の契約
・不動産の売買
・預貯金の引き出し
・相続手続(遺産分割協議書の作成など) 等
認知症などになると、このような手続きをひとりで行うのは困難です。これらの行為をスムーズに進めるためには、成年後見人が必要となるでしょう。

任意後見制度と法定後見制度の違い
成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つがあり、内容が異なります。
・任意後見制度
任意後見制度は、本人の判断能力があるうちに、自分の意思で後見人を選べる仕組みです。後見人にご家族や親族の方を指名できることが、大きなメリットであり、契約内容や後見人への報酬も全て自分で決定できるため、非常に自由度の高い制度となっています。
ただし、判断能力がなくなってしまってからでは、任意後見制度を契約することはできません。まだ早いとお思いの方もいらっしゃるかも知れませんが、いざという時のために、一日でも早くご家族と話し合い、準備をしておくことが大切です。
・法定後見制度
法定後見制度は、本人の判断能力が低下した際、家庭裁判所が後見人を選定する仕組みです。本人や家族が後見人を選ぶことはできず、後見の内容もあらかじめ決まっています。また、後見人へは毎月、報酬を支払っていくことになります。
後見制度は見守り契約と併用を
任意後見制度は、判断能力が低下した際に初めて、その効力が発動されます。そのため、判断能力に問題がないかを、定期的に確認しなければなりません。
ご両親が遠方に住んでいて難しい場合は、専門の業者などが行っている見守りサービスなどと契約すれば、電話連絡や訪問を通してご両親の様子を見てもらうことが可能です。
▼成年後見制度についてもっと詳しくお知りになりたい方はぜひこちらの記事もご確認ください▼
『任意後見制度と法定後見制度|おひとりさまにも大きなメリット!』

生前整理
生前整理とは、生前の元気なうちに、身の回りのものや財産を整理しておくことです。生前整理をしておくことで、万が一の際にはご遺族の負担がとても軽くなります。
高齢のご両親だけで行うことが難しい場合は、年末年始などの機会に手伝ってあげるのもおすすめです。
ここでは、生前整理について、以下の2点を詳しく説明します。
・生前整理を行わないリスク
・生前整理の進め方

生前整理を行わないリスク
生前整理を行わないままご逝去されると、残されたご家族は次のようなことで困ってしまいます。
・必要なものと不要なものの選別に時間がかかる
・不用品を処分するための費用がかさむ場合がある
・コレクションの品などは価値が分かりにくく処分が難しい
また、近年ではスマートホンやパソコンが普及したため、デジタル遺産のリスクも高まっています。デジタル遺産とは、データ形式の財産のことで、デジタル遺品とも呼ばれます。
デジタル遺産があると、次のようなトラブルが起こりがちです。
・スマートホンやパソコンのロック解除ができない
・SNSのアカウトを削除できない
・どのネット銀行やネット証券を利用していたのか分からない
・解約できていなかった月額サービスから毎月料金が引き落とされる
デジタル遺産はその特性上、ご遺族であっても簡単に整理することは難しいものです。エンディングノートにパスワードを書いておいてもらうなど、いざという時の対策を取っておくといいでしょう。

生前整理の進め方
生前整理の進め方にはそれぞれ違いがありますが、何から始めていいのか迷ってしまう方は、次の順番で考えてみてはいかがでしょうか。
・不用品の処分
・エンディングノートを作成する
・遺言書の作成
不用品を処分する作業には、気力や体力が必要です。お元気なうちでなければできないことですから、始めるタイミングに早すぎるということはありません。身の回りの品の整理をすることで、認識していなかった財産を把握できることもあります。
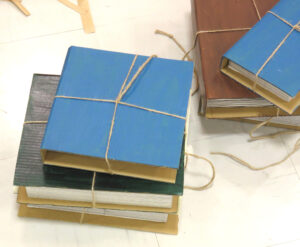
年末年始の時間を有意義なものにしましょう
遺言書や成年後見制度、生前整理などは、生死や認知症に関わる話ですから、話題にしにくいと感じる方もいらっしゃるかも知れません。しかし、ご両親がさらに年を重ねたころには、より現実味が増し、今よりももっと話題にし難くなってしまいますし、先延ばしにしている間にもしものことが起こる可能性もあります。
終活の話し合いに、早すぎるということはありません。年末年始、久々に家族が集まる暖かい時間に、ご両親とコミュニケーションを取るつもりで切り出してみてはいかがでしょうか。

テラスライフでは、自筆証書遺言、公正証書遺言の作成サポート、成年後見制度のご契約サポートなど、終活に関するお手続きなどを総合的にお手伝いさせていただいております。
お客様のお話しを徹底的に伺い、ご希望に添える制度などをご紹介、ご提案に加え、難しい手続きなどは代行致しますので、どんなお悩みでもお気軽にご相談ください。もちろん、お見積り・ご相談は無料です。
テラスライフ電話番号:045-370-7085
(監修:行政書士・尾形達也)
- 任意後見
- 成年後見制度
- 法定後見
- 相続
- 終活
- 老後の備え
- 自筆証書遺言
- 認知症
- 財産管理
- 遺言書

- おひとりさま
- おひとり様
- エンディングノート
- コミュニティ
- 不動産分割
- 人生設計
- 介護施設見学の同行
- 仕事付き高齢者向け住宅
- 仕事付き高齢者向け施設
- 任意後見
- 任意後見制度
- 保証人
- 入院
- 入院準備
- 公正証書遺言
- 共済年金
- 喪主代行
- 埋葬手配
- 家族信託
- 年金手続きサポート
- 延命措置
- 想いを伝える
- 成年後見人
- 成年後見制度
- 手術の立ち会い
- 施設見学
- 日常生活を支援
- 死亡一時金の申請
- 死亡届
- 死後事務委任契約
- 法定後見
- 法定後見制度
- 法要代行
- 海洋散骨
- 生前贈与
- 相続
- 相続放棄
- 相続登記
- 相続税
- 相続調査
- 福祉型信託
- 空き家
- 納骨代行
- 終活
- 老後の備え
- 老後資金
- 老齢厚生年金
- 自分の意志
- 自筆証書遺言
- 自筆証書遺言保管制度
- 葬儀サポート
- 要介護
- 要介護認定
- 要支援
- 認知症
- 象族税対策
- 財産管理
- 財産管理のトラブル
- 財産管理委任契約
- 身元保証
- 身元保証人
- 身元引受人
- 身辺監護
- 連帯保証人
- 遺品整理
- 遺族厚生年金
- 遺族基礎年金
- 遺族年金
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議書
- 遺留分
- 遺留分侵害額請求
- 遺言
- 遺言公正証書
- 遺言執行人
- 遺言書
- 遺贈寄付
- 配偶者居住権
- 配偶者短期居住権
- 障害厚生年金
- 高齢者施設